車のオイル交換は重要なメンテナンスのひとつです。車で使用されているオイルにはいくつかの種類がありますが、メンテナンス時に「オイル交換」として呼ばれる際のオイルは一般的に「エンジンオイル」を指します。
車に乗っていても、オイル交換をするタイミングやエンジンオイルの違いなど、意外とわからないことは多いものです。そこで、オイルの基本的な役割や種類と選び方、交換時期、セルフ交換の方法などをご紹介します。
この記事のPOINT
- エンジン性能を維持するためにエンジンオイルは定期的な交換が必要
- オイル交換のタイミングは、走行距離やエンジンオイルの状態から知ることができる
- オイル交換は業者に依頼するほか、自分でも行える
車のオイル交換の適切なタイミングとは

エンジンオイルの交換のタイミングは、車の走行距離やオイルの交換頻度、オイルの状態を基に判断できます。
走行距離とオイルの交換頻度による見極め方
エンジンオイルの交換のタイミングは、ディーラーやガソリンスタンドなどの業者で確認してもらったり、各自動車メーカーが提示するオイル交換の目安を参考にしたりする方法があります。また、車種によってさまざまではありますが、前回のオイル交換からの走行距離や交換頻度で判断することもできます。
〈オイル交換のタイミングの目安〉
| 一般ガソリン車 | ・前回交換してから走行距離が軽自動車で2,500~5,000km、普通車で5,000~15,000kmを超える ・1年に1回 |
| ターボ付きガソリン車 | ・前回のオイル交換から走行距離が5,000kmを超える ・半年に1回 |
| ディーゼル車 | ・前回のオイル交換から走行距離が5,000~20,000kmを超える ・半年に1回 |
※車種によって異なる
一般ガソリン車:走行距離2,500~15,000kmを超える、または1年に1回
普通車や軽自動車といった一般的なガソリン車の場合は、前回オイル交換を行ってから走行距離が軽自動車で2,500~5,000km、普通車で5,000~15,000kmを超えた時期、または1年に1回がオイル交換の目安となります。
一般的なガソリン車はターボ車やディーゼル車に比べてエンジンオイルの劣化が緩やかなため、交換ペースも比較的遅くなります。
ターボ付きガソリン車:走行距離5,000kmを超える、または半年に1回
ターボ付きのガソリン車は、前回のオイル交換から走行距離が5,000kmを超えた時期、または半年に1回が目安です。
ターボエンジンは強いエネルギーを生み出すため、一般的なエンジンよりも冷却作用に負荷がかかる構造になっています。冷却にはエンジンオイルが使われるため、ターボ車は一般車よりエンジンオイルが早く劣化します。
ディーゼル車:走行距離10,000kmを超える、または1年に1回
ディーゼルエンジンを搭載した車は、前回のオイル交換から走行距離が10,000kmを超えた時期、または1年に1回がオイル交換の目安とされています。
ディーゼルエンジンには燃料として軽油が用いられています。エンジンオイルは軽油に含まれた硫黄分が酸素と結びついて発生する硫酸を中和する役割を担っています。さらに、ディーゼルエンジンでは稼働中にすすが出やすいことから、エンジンオイルは一般車に比べて早く劣化してしまいます。
なお、輸入車、特にヨーロッパの車は、オイル交換のサイクルが国産車より長いケースが多く、これは海外の道路環境におけるエンジンオイルへの負担が基準となっているためです。日本で走行する場合は、エンジンオイルへの負担は国産車と同じになることから、国産車と同様のサイクルでオイル交換を行うのが望ましいでしょう。
エンジンオイルの状態による見極め方

より適切なオイル交換の時期を知りたいときは、エンジンオイルを直接チェックするのが一番です。エンジンオイルの状態は、エンジンに付属するオイルレベルゲージで知ることができます。
次に挙げるチェックポイントに沿って、エンジンから引き抜いたオイルレベルゲージに付着したオイルの状態を確認してみましょう。
エンジンオイルの量が少ない
エンジンオイルの量が減っていないかチェックすることが、オイル交換のタイミングをはかる最も簡単な方法です。
オイルレベルゲージには、上限と下限を示す2つのマークが刻印されています。オイルの跡がマークのあいだにあればエンジンオイルの量が足りている状態ですが、下方のマークに近い場合や、下方のマークよりも下に付いている場合はオイル交換が必要です。

エンジンオイルが汚れている
オイルレベルゲージについたオイルをウエスなどで拭き取り、オイルレベルゲージをオイル内に戻します。再度ゲージを引き出して、白いウエスやキッチンペーパーなどにオイルを垂らします。
オイルにスラッジ(汚れ)が混じって黒く変色している場合はオイルが劣化しているため、交換を行いましょう。
エンジンオイルが漏れている
車の下にオイルが染み出していないか、エンジンの周辺もチェックしましょう。オイルが溜まっている場合は漏れている可能性があります。
なお、異常がないように見えても、オイルの減りが早い場合はオイル漏れを起こしている可能性があります。そのような状況を判断するためにも、定期的にオイルの状態を確認する習慣をつけておきましょう。
また、エンジンオイルをチェックするときは、必ずエンジンをストップし、エンジンが冷めるのを待ちましょう。動いているエンジンは非常に高温なため、冷える前に点検するとやけどの危険性があります。
オイル交換を業者に依頼する場合の料金と作業時間
エンジンオイルの交換は、ディーラーやカー用品店、ガソリンスタンド、整備工場などに依頼するのが一般的です。依頼先を選びやすいように、それぞれの料金の相場やメリットとデメリットを知っておきましょう。
なお、エンジンオイル自体の料金は、ガソリンスタンドやカー用品店などでは2,000~6,000円程度ですが、ディーラーでは10,000円近くになることもあります。エンジンオイルの種類や量にもよりますが、オイルにかかる費用も含めて依頼先を検討することが大切です。
〈オイル交換を依頼できる業者の特徴〉
| 工賃の目安* | 作業時間の目安 | メリット | デメリット | |
|---|---|---|---|---|
| ディーラー | 1,000〜2,000円 | 20〜30分 | ・純正オイルを使用する ・安心して依頼できる(整備保証がつくことが多い) | ・交換工賃が高め ・希望のエンジンオイルを使用できない |
| カー用品店 | 500円 | 20〜30分 | ・取り扱うオイルの種類が豊富 ・会員だと工賃が無料になることがある | ・休日は混みやすく待ち時間が長くなる ・店内商品のオイルから選ぶ必要がある |
| ガソリンスタンド | 1,000円 | 30分以内 | ・比較的遅めの時間まで対応してくれる ・作業時間が短め | ・整備士の技術力にばらつきがある ・交換工賃が高め |
| 整備工場 | 整備工場による | 20〜30分 | ・なじみの工場があれば気軽に相談できる | ・希望するオイルを置いていないことがある |
*交換用オイルの費用が別途必要
ディーラーで交換する
自動車メーカーの特約店であるディーラーでは、自社の車に精通した専門の整備士が、メーカー純正のオイルを使用して作業を行ってくれるため、車に最適なオイルに交換できる安心感があります。
その一方で、自分の好きなエンジンオイルを使用してもらうといったことはできません。
作業時間は20〜30分ほどで終了することが多いです。工賃はおよそ1,000~2,000円程度で、ほかの業者と比べて、交換用のオイル、作業工賃ともに高くなる傾向があります。
カー用品店で交換する
カー用品店はピットサービスでオイル交換を受け付けています。エンジンオイルを多数取り扱っており、好きなオイルを選ぶことができます。作業時間はおよそ20〜30分で、作業工賃の相場も500円ほどと安めな上、会員登録などで無料になることもあります。
予算や好みに応じてオイルを選べ、迷ったときはスタッフに相談できるというメリットがありますが、土日などは待ち時間が長くなりやすいほか、店舗によっては取り扱うオイルの種類が限られることもあります。
ガソリンスタンドで交換する
ガソリンスタンドでは、給油のついでにオイル交換が可能です。作業時間は予約なしでも30分以内に終わるケースが多いですが、工賃の相場は1,000円以内とカー用品店より少し高めです。
店舗によって整備士の知識や技術力にばらつきがあるため、信頼できるところを選びましょう。なお、24時間営業の店舗などでは比較的遅めの時間までオイル交換に対応してくれるので、自分のペースで依頼しやすい点がメリットです。
整備工場で交換する
整備工場は、さまざまな車種に対応できる技術力を持つ整備士が作業してくれるので、安心して車を預けられます。オイル交換の作業時間は20〜30分ほどで、工賃は整備工場によってまちまちですが、長年の付き合いがあるような場合は無料で交換してくれることもあります。
なお、整備工場は少人数で経営している店舗が多いため、予約しておくほうが安心です。また、小さな整備工場では在庫が限られるため、使用したいオイルが決まっている場合は事前に確認しておきましょう。
車のオイル交換を自分で行う方法
オイル交換は、ディーラーやガソリンスタンドなどに依頼するほか、セルフで行うことも可能です。
エンジンオイルを自分で交換するには「上抜き」と「下抜き」という2つの方法があります。それぞれの作業手順を確認して、自身に合った方法で行いましょう。
〈エンジンオイルを自分で交換する方法〉
| 上抜き* | ・オイルタンクの中に溜まった古いエンジンオイルを、オイルチェンジャーと呼ばれる専用ポンプで吸い上げる方法 ・ジャッキアップなどのリフト作業がいらない ・オイルチェンジャーなど専用の道具を購入する必要がある |
| 下抜き | ・オイルドレンボルトを開くことで、古いエンジンオイルを抜き出す方法 ・オイル交換といっしょに車の下回りのチェックができる ・上抜きと比較して、古いオイルを抜きやすい ・ジャッキアップして作業する必要がある ・専用の工具を用意する必要がある |
*車種によっては行えない場合がある
準備する物

- 新しいエンジンオイル
- オイルフィルター(オイル交換2回に1回の交換が目安)
- 廃油処理箱
- めがねレンチ
- トルクレンチ
- オイルジョッキまたはじょうご
- パーツクリーナー
- ゴムグローブ
- ウエス
- オイルチェンジャー(上抜きのみ)
- ドレンボルトの交換ワッシャー(下抜きのみ)
- ジャッキと輪止め、リジッドラック(下抜きのみ)
エンジンオイルのセルフ交換手順(上抜き)
1. 暖気運転してエンジンオイルを温め、オイルを吸い上げやすくする。
2.エンジンを止めたらボンネットを開け、オイルチェンジャーのノズルをオイルパンの底に届くまでしっかり差し込む。
3. オイルチェンジャーで古いエンジンオイルをポンプアップする。
4. じょうごかオイルジョッキを使って、新しいオイルを注ぐ。
5. オイルレベルゲージをチェックし、オイルが適量まで入ったか確認する。
エンジンオイルのセルフ交換手順(下抜き)

1.エンジンを切ったら、ジャッキアップする対角線上のタイヤに輪留めを行い、ジャッキアップする。その後、リジッドラックを掛ける。

2.廃油処理箱をセットし、オイルキャップとドレンボルトを外して古いエンジンオイルを抜く。

3.古いオイルがすべて抜けたら、ドレンボルトに新しいワッシャーをはめ込んで規定トルクで締める。

4.ジャッキを下ろして車を戻し、じょうごやオイルジョッキを使って新しいエンジンオイルを入れる。

5.オイルレベルゲージをチェックして適量になったかどうかを確認する。
自身でエンジンオイルを交換する際の注意点
エンジンオイルを自分で交換する場合には、留意点があります。安全を確保した上で作業を行わないと、事故の原因になることもあるので注意しましょう。
新しいエンジンオイルは適切な量を入れる
セルフ交換で失敗しがちなのが、エンジンオイルの量です。多すぎたり少なすぎたりしても以下のようなトラブルにつながります。
エンジンオイルが多すぎる場合
オイルレベルゲージの上限より多くオイルを入れた場合、そのまま走行すると未燃焼の混合気であるブローバイガスが増えてエアクリーナーが汚れやすくなります。また、オイルがエンジン内にあふれてしまい、マフラーから白煙が出たり、エンジンが回りにくくなって燃費性能が低下したりする可能性もあります。
エンジンオイルを入れすぎた場合はポンプなどを使って吸い出すか、車両底部から抜きましょう。ディーラーなどに持ち込んで抜いてもらうことも可能です。
エンジンオイルが少なすぎる場合
冒頭で解説したとおり、エンジンオイルにはさまざまな役割があります。そのため、オイルが少なすぎる場合には、エンジンの機能が低下したりオーバーヒートしたりしてしまいます。メーカー指定の量をしっかり確認して交換するようにしましょう。
古いエンジンオイルは正しく廃棄処理を行う
オイルタンクから抜き出した古いエンジンオイルの処分方法は、自治体によって異なります。廃油パックを利用すれば普通ゴミとして捨てることができますが、廃油をゴミに出せない地域の場合はガソリンスタンドやオイル購入店に持ち込んで処分してもらいましょう。
料金は店舗によって異なるほか、販売店によっては新しいオイルの購入が条件になることもあるので、購入時に確認しておくと安心です。
古いエンジンオイルをできるだけ抜いてからオイル交換を行う
オイル交換をする際に、オイルタンクに残った微量の古いオイルと新しいオイルが混ざる分には問題ありません。ただ、古いオイルが多量に残った状態で新しいオイルを補充すると、性能が落ちる可能性があります。
オイル交換の際は、できる限り古いオイルを抜いてから新しいオイルを入れることをおすすめします。
なお、未使用の新しいオイル同士なら、グレードの異なるオイルが混ざることに問題はないとされています。ただし、粘度の違うオイル同士が混ざると成分のバランスが崩れてしまい、オイルの性能が発揮されない可能性があるので、基本的にオイルが混ざるような状態は避けたほうが無難でしょう。
車のエンジンオイルの種類と選び方

エンジンオイルにはたくさんの種類がありますが、いずれも「ベースオイル」「オイルの粘度」「オイルの規格」の3つの要素に基づいて選択できます。
自身の車や状況によって最適なオイルを選ぶためには、エンジンオイルの種類と特徴を理解した上で、重視する要素から選ぶのが望ましいでしょう。
なお、価格はオイルによってさまざまですが、安いオイルを利用していても交換をこまめに行うことでエンジンを常にきれいに保てたり、季節や地域によっては安いオイルのほうが適している場合もあったりします。必ずしも高いオイルがいいとは限りません。
ベースオイルで選ぶ
ベースオイルはエンジンオイルのベースとなる成分のことです。ベースオイルがどのような成分由来かでエンジンオイルの性能が大きく左右されるため、エンジンオイルで最も重要な要素といえます。
ベースオイルにはおもに鉱物油、化学合成油、部分合成油の3種類があり、値段の安さで選ぶなら鉱物油、品質で選ぶなら化学合成油、バランスの良いものを選びたいなら部分合成油というのが基本的な考え方です。
〈ベースオイルの特徴〉
| 特徴 | メリット | デメリット | |
|---|---|---|---|
| 鉱物油 | ・一般的なベースオイル ・原油から不純物を除去して精製されたもの | 値段が安い | 耐熱性、耐久性が劣る |
| 化学合成油 | ・最高性能のベースオイル ・不純物が少ない | 性能が高い 冬場に強い | 値段が高い |
| 部分合成油 | ・鉱物油と化学合成油をブレンドしたベースオイル ・揮発性が高い | 性能とコストのバランスがいい | 化学合成油より性能が劣る |
オイルの粘度で選ぶ
エンジンオイルによって粘度に違いがあり、粘度が高いほど固く、粘度が低いほどサラサラとした柔らかいオイルになります。
車によって適したエンジンオイルの粘度は異なり、車種ごとに指定があります。
指定粘度の範囲内のエンジンオイルを選ぶのが基本ですが、走行距離が長くなった車や登録から年数が経った車は粘度を少し上げるのもひとつの方法です。摩耗によって生じたエンジンの部品の隙間をエンジンオイルが埋めてくれます。
なお、エンジンオイルの粘度は「10W−50」といったように数字とアルファベットの組み合わせで表記され、左はエンジンの始動に差し支えない外気の温度、右は油膜切れを起こさないエンジンオイルの温度を表しています。
また、左にのみ表示されたWはWinterの頭文字で、5Wは-30℃、10Wは-20℃など、数字に対応する外気温を示しています。
〈オイルの粘度による違い〉
| オイル粘度 | ←低粘度オイル 高粘度オイル→ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 粘度指数 (低温) | 0W | 5W | 10W | 15W | 20W |
| 粘度指数 (高温) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| 特徴 | 低温時・冷間時でも素早く動く 燃費がいい 高温時に油膜切れを起こしやすい エンジン音が大きくなる | 低温時・冷間時の始動性が悪い 燃費が悪い 高温時でも油膜をキープできる エンジン音が静か |
|||
オイルの規格で選ぶ
エンジンオイルには、おもに「API規格」「ILSAC規格」「JASO規格」の3つがあり、各自動車団体が独自の基準に応じて燃費性能や蒸発性、耐摩耗性、酸化安定性などの審査項目によってグレードを定めています。
API規格
APIはAmerican Petroleum Instituteの略で、米国石油協会(API)、アメリカ材料試験協会(ASTM)、アメリカ自動車技術者協会(SAE)の3社が定めるエンジンオイルの規格です。「SH」「CF」など2文字のアルファベットで表記され、1つ目の文字は対応車種を、2つ目の文字はオイルの性能を示しています。
〈API規格の記載ルール〉
| 1つ目のアルファベット | 車のタイプ(ガソリン車はS、ディーゼル車はC) |
| 2文字目のアルファベット | 総合的な性能の高さ(Aから始まり、後に進むほどオイルの燃費性能や蒸発性、酸化安定性などの性能が高い) |
車に適したグレードは取扱説明書に記載されており、指定されたグレードよりも前のアルファベットのものを使用すると、エンジンが本来の性能を発揮できません。
なお、API規格はガソリン車においては一般的ですが、ディーゼル車では国産のクリーンディーゼルエンジンに対応しているJASO規格がおもに使用されています。
ILSAC規格
国際潤滑油規格諮問委員会(ILSAC)が定めた規格で、API規格に省燃費性能を加えたものです。グレードはGF-1〜GF-6の6つで、数字が大きいほど高性能オイルになります。なお、GF-1はAPI規格のSHに相当し、以降も順に対応しています。
2020年に制定された最新のGF-6はAPI規格の「SP」に相当し、2023年2月時点では省燃費性能や清浄性などが最も高いグレードです。
JASO規格
国産クリーンディーゼルエンジンに対応したディーゼルエンジン専用オイルの日本独自規格です。乗用車に適したオイルはDL-1やDL-2と表記されています。
車のエンジンオイルの役割は?オイル交換しなかったらどうなる?

エンジンオイルは、エンジンの内部を循環してエンジンを正常に動かす役割を担っています。エンジンを車の心臓に例えるなら、エンジンオイルはいわば車の血液です。それだけに、エンジンオイルの状態は車の走行にも大きな影響を及ぼすことから、定期的に交換して、最適な状態を維持する必要があるのです。
エンジンオイル5つの役割
車を動かすために必要不可欠なエンジンオイルには、おもに次に挙げる5つの役割があります。
1.潤滑
・燃料が燃えた際に出るすすやほこり、金属が摩耗して出る粉末などがエンジン内部に溜まらないようエンジンの金属部分に油膜を張り、動きを滑らかにすることで、燃費性能の低下や、エンジン異常を防ぐ
2.冷却
・燃焼や摩擦によるエンジンの熱を吸収し、オーバーヒートを防ぐ
3.密封
・ピストンとシリンダーの隙間を埋めて、燃焼による圧力を逃がさないようにし、エネルギー効率を保つ
4.洗浄
・オイルの燃えカス(スラッジ)がエンジンの内壁に堆積しないよう、エンジン内部を循環して汚れを吸着・分散させてエンジンの働きが低下するのを防ぐ
5.防腐
・エンジンの金属部分をコーティングするとともに、エンジン内部に発生した水分を取り込んで錆を防ぐ
エンジンオイルを交換しなかったらどうなる?
エンジンオイルはエンジンが摩耗や錆などで劣化しないように保護し、効率よくエネルギーが作り出せるように汚れや水分を取り込みながら循環しています。
エンジンを動かすほどオイルは劣化するため、そのままにしているとエンジン本来の性能を発揮できなくなってしまいます。その結果、燃費が下がったり、オイルの循環が滞ってエンジンの焼き付きが生じ、最悪の場合は車両火災が起きたりする場合があります。
エンジンオイルは交換しすぎても良くない?
エンジンオイルは新品のときが最も性能が高く、走行するにつれてだんだんと性能が落ちてきます。そのため、車への影響やエンジン性能という面から見ると、交換頻度の高さ自体がマイナスになることはありません。
ただし、オイルパンや燃料のタンクについている、排液用の口をふさぐためのオイルドレンボルトの締め付けトルクが守られていない場合、交換頻度が高いことでオイルパンやオイルドレンボルトを破損する可能性が高まります。
また、まだ使用できる状態のエンジンオイルを破棄することはサスティナビリティの見地から問題視されるケースもあるかもしれません。
エンジンオイルは指定のものを使用するほうがいい?
エンジンオイルは、粘度とグレードが車ごとに指定されています。新車の状態でその車のエンジンの性能を最も活かせるエンジンオイルが指定されているので、原則として粘度は指定されているものを使用しましょう。グレードは、指定されているものよりも高ければ使用できる場合がほとんどです(旧車を除く)。
なお、必ずしも純正のオイルである必要はありません。純正オイルは性能が保証されているので安心ですが、純正でなくても、指定の粘度で、かつ車の性能を活かせるグレードであれば問題なく使用できます。
車のオイル交換といっしょに行いたいメンテナンス
オイル交換をするときには、エンジン周辺の状態もチェックして、いくつかのメンテナンスも併せて行うと、オイルの寿命を延ばすだけでなく、運転性能を高めて維持費を抑えることができます。
エンジンフラッシング
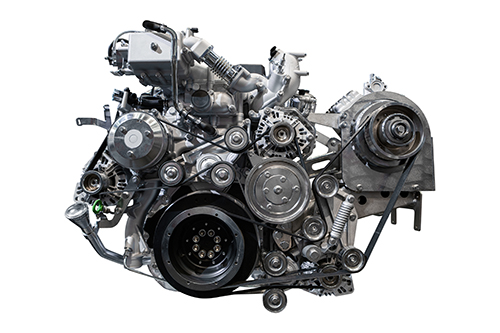
フラッシングとは汚れ落としという意味で、オイル交換をする際にいっしょに行われることの多いメンテナンスです。古いエンジンオイルに洗浄剤を混ぜてエンジンを回す方法と、古いオイルを抜き出した後に専用のフラッシングオイルを入れてエンジンをかける方法があります。
ドロドロになったスラッジ(汚れ)はエンジンオイルで吸着することができないため、エンジンフラッシングを行うことでエンジン内をリフレッシュできます。エンジンフラッシングをしてから新しいオイルを入れると、エンジンオイルをきれいな状態で長く保つことができます。
オイルフィルター交換

オイル交換といっしょに行うことが多いのが、オイルフィルターの交換です。オイルフィルターはオイルが取り込んだ汚れを濾過して、オイルをきれいな状態に保つ働きをしています。
濾紙はアコーディオン状になっているため、固形の汚れをキャッチしやすい反面、詰まりやすくもあります。フィルターの目が詰まるとオイルフィルターの性能が下がるので、定期的な交換が必要です。オイル交換2回につき1回のサイクルが目安とされています。
注意!車のエンジンオイルの劣化を早めてしまう乗り方

車の乗り方や状況によってはエンジンオイルの劣化を早めてしまうケースがあります。劣化につながる条件を「シビアコンディション」といい、具体的には以下のようなケースを指します。
〈シビアコンディションとされるおもな条件〉
- 運転時に衝撃を感じる荒れた路面、車の下回り部分に跳ね上がった石が当たることが多い路面や轍など、ほこりが多い路面
- 雪道
- 走行距離が年20,000km以上
- 山道、登降坂路:登り下りが多く、ブレーキの使用回数が多い路面
- 1回につき8km以下の短距離での繰り返し運転
- 氷点下での繰り返し運転
- 時速30km以下の低速走行
- 1日2時間以上のアイドリング
シビアコンディションは自動車メーカーが独自に定めたもので、近所のスーパーや駅まで車を使う「ちょい乗り」や、渋滞が多い道でアイドリングを繰り返す場合も該当します。
エンジンにかかる負荷が大きく、エンジンオイルの寿命を縮めやすいです。オイル交換時期は、メーカーや車種によっても異なりますが、一般的なコンディションのおよそ半分が目安となるケースが多いです。
例えば、一般ガソリン車の場合、「前回のオイル交換から走行距離15,000kmを超える時期、または1年に1回」が通常のオイル交換の頻度ですが、シビアコンディションでは前回のオイル交換から走行距離が7,500kmを超える時期、または6ヵ月となります。
シビアコンディションで運転する機会が多い場合は、早期の交換が必要になることに注意しましょう。
よくある質問
Q1:車のオイル交換の時期は?
A:車種によりますがガソリン車の場合、一般的に軽自動車で2,500~5,000km、普通車で5,000~15,000kmを超えた時期、または1年に1回です。エンジンオイルの状態で判断することもでき、残量や汚れ具合をオイルレベルゲージで確認します。
Q2:オイルの種類はたくさんあるけれど、どれを選べばいい?
A:エンジンオイルの種類は、主成分であるベースオイルや粘度、規格によって分類されています。それぞれに性能や適した環境、価格などが異なるため、特徴を理解して、自身の車や走行環境に合ったものを選びましょう。
Q3:エンジンオイルを交換しないとどうなるの?
A:エンジンオイルは、エンジン内において、潤滑、冷却、密封、洗浄、防腐といった5つの役割を担っています。使い続けることで汚れが溜まるなどして劣化し十分な役割を果たせなくなると、燃費が下がったり、最悪の場合は車両火災が起きたりします。
※記事の内容は2023年2月時点の情報で制作しています。









