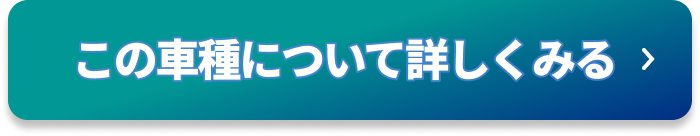2022年6月にFRベースのプラットフォームに6気筒エンジン、トルコンレス8ATなど、数々の新開発メカニズムとともに登場したマツダ「CX-60」(326万7000円〜646万2500円)が、2024年12月、マイナーチェンジを受けました。突き上げが気になるサスペンションや、ぎこちなさのあったトランスミッションなどに大改良を加えたとするラグジュアリーSUVに島崎七生人さんが試乗しました。
テストコース外でしっかり乗り、市場の声も踏まえた

XD L Packageの外観、メインカットのマシングレーのモデルはXD-HYBRID Premium Modern
この機会に改めて書かせていただくと、僕は日頃から仕事でクルマに乗り、こうした試乗記事を書くときに、基本姿勢として断定的あるいは頭ごなしに「これでは駄目だ」「ここはこうすべきだ」といった物言いはしない。ユーザーの夢を壊したくないという思いもあるが、肩書きはモータージャーナリストで、その立場で年間に試乗、取材で乗るクルマは週に1〜2台かそれ以上のペース。最近は短時間ではなく、時間を融通してもらいなるべくジックリと乗るようにもしているが、それはあくまでもユーザー目線で“もしもこのクルマのオーナーになったら、どんなことを感じ、どういう思いができるか”を肌で感じ、実体験したいから。
それゆえ、たとえば自動車メーカーの開発エンジニアの方と話をする機会に「どうでしたか?」と訊かれた場合、こう感じた、(こちらのささやかな経験値をもとに)○○車と較べてこう思った、ここがこうならなおいいと思った……と伝えるようにしている。開発エンジニアはプロ中のプロであり専門的な知見、ノウハウをもち、コチラの指摘など先刻ご承知のはずだ。だからといって謙(へりくだ)るだけではないが、“ユーザーならこう思う”をユーザーの代弁者になりエンジニアに伝えることで、何か参考になることがあればいい……と思う。

ここでCX-60の最新モデルの話に進む。聞けば2022年6月に登場したCX-60は「開発初期はMBD(モデルベース開発)が先鋭化した時期で、コロナ禍とも重なった」(車両開発推進ご担当の増井芳行さん)といい、「今回はテストコースの中だけでなく外でもしっかり乗り、市場の声も踏まえながら、気になるところを削ぎ落とす……そんな作り込みをした」(同)のだそう。
サスペンションの乗り心地だけでない多岐にわたる改良

ハイエンドグレードのXD-HYBRID Premium Modernの上質で贅沢なインテリア

ハイクラス(価格的には真ん中)のXD L Packageはブラック(グレージュも設定あり)の本革シートを採用

スタンダードモデルのXD SPのインテリアはスポーティなブラック基調
実車の試乗後、この話を聞いて、僕は「なるほど、そういうことか」と思った。なかでもサスペンションは、実は2023年末、すでにリアのダンパーの変更が行なわれていたのだが、今回の改良ではより広範囲に改良の手が入れられた。とくに登場後に声のあがった乗り心地への対策として、前後ダンパーの減衰力が上げられたほか、リアについてはスプリングのバネ定数が下げられ、スタビライザーの廃止、クロスメンバーブッシュ特性の見直しなどを実施。一方でフロントでは、ナックル締結ポイントを改める構造変更を実施。これはサスペンションがストロークした際(沈み込んだ際)のオーバーステア特性をアンダー方向に寄せ、安定性を求めたもので、プラットフォームが共通のCX-80ではすでに採用済みのものだという。そのほか、電動パワーステアリング制御の見直しによる操舵フィールの最適化ほか、AWD & KPC & DSC制御の最適化、8速ATのクラッチ制御の進化など、サスペンション以外の改良も多岐にわたっている。
シャープさは残しながら少し穏やかな方向に

XD-HYBRID Premium Modern

XD L Package

XD-HYBRID Premium Modern

「全体的に少し穏やかな方向にした。元々のプラットフォームが、ハンドリングに対してかなりシャープな作り。なのでシャープさは残したまま、きれいな路面でハンドルをゆっくり切るシーンではSUVながらキレイにスッキリ曲がる。乗り心地は街中で以前はガツガツと来たところを穏やかにした。ナックルの締結ポイントも変え、ニュートラルステア寄りの弱アンダーをよりアンダー方向とし、直進性を含め安定方向に。とはいえもともとの回頭性のよさは維持し、ワインディングではしっかりとフィードバックがあるため、自信をもって曲がれるようになっている」と、開発本部・操安性能開発部の下﨑達也さんは今回の改良についての狙いを話す。下﨑さんにはCX-80も担当されており、その時にもお話を伺った方だ。
CX-80に遜色のない快適性、洗練度が実感できる

スタンダードモデルのXD SPはホイールやミラーがブラックとなる。タイヤサイズは235/50R20で上級モデルと同じだ
では実際に走らせての印象はどうだったのか? 今回は試乗会に参加、XD-HYBRID Premium Modern、XD SP(以上は4WD)、そしてXD L Package(FR)の3台が割り当てられた。いずれにしても限られた時間内だったため、“初見”ということになり、断定的なことの報告はまた別の機会に改めたいが、言えることは、CX-80が登場した現段階でも、CX-80に遜色のない快適性、洗練度がこのCX-60でもより実感できるようになったという点。

とくに割り当てられた3車はいずれも235/50 R20 100WサイズのBS・ALENZA 001(ENLITEN)が装着され、このタイヤの持ち味が乗り味にしなやかさを加味している印象をもった。その上で、街中主体の試乗ではあったが、走行中のボディのフラット感は実感したところ。さらにステアリングフィールについて、パワーアシストの立ち上がるタイミングと量がこれまでよりも的確になり、平たく言うと、直前のモデルまでは操舵にやや重さを感じたものから、操舵感、安定感は残しつつ、よりスムースなタッチになったと感じた。
制御がより精緻になった8AT

それとトルクコンバーターを廃しクラッチを持つユニークな8速ATに関しても進化を感じた。とくにごく小さな段差を乗り越えながら発進をかけようするような際、これまでは場面により僅かな振動とギクシャク感が誘発されていたもの。が、新しいクルマではそうした事象は見られず、アクセルの踏み加減に気を使わずに走らせられるようになった。 制御がより精緻になったということなのだろう。
SUVであってもスポーティな走りは外せないマツダらしさ

しなやかな身のこなしに爽快感すら覚えるXD L PackageのFRモデル
また今回の試乗で、実は「ほほぉ」と思わせられたのが実は試乗車中で唯一のFR車だったXD L Package。ディーゼル搭載車中では車重がもっとも軽く(といっても1820kg。同仕様の4WDは1870kg)、そのせいもあり、ちょっとしたワインディングを抜けてみると、クルマの挙動とステアリングフィールが非常に自然に感じられ、しなやかな身のこなしには爽快感すら覚えたほどだった。「車重でいうとマイルドハイブリッドはフロントが1番重たい。反対にFRは1番軽い。でもダンパーは同じなので、FRのほうがダンパーの減衰力は相対的には高いことになり、その分、応答性がよくなる。二駆と四駆では四駆もFRに使いセッティングはしているが、FRはフロントにまったく駆動力がかかっていないので、ニュートラル感は強い」とは前出・下﨑さんの説明。「ダンパーはフロントは共通、リアはMHEVとノンHEVは同じ、FRのリアダンパーは違う」(下﨑さん)こともあり、FRの場合、荷重をしっかりとかけて駆動力を伝える……そんな考え方も盛り込まれているのだろう。

以前にマツダ3のベースモデルに乗った際、素直な身のこなしに“FFのロードスター”などと思ったものだが、さしずめCX-60のこのFRの走りっぷりは“SUVのロードスター”と書いてしまおうかと(←書いているが)思ったほど。そしてこのFRの走りを実感して、マツダとCX-60の開発エンジニアは、SUVであってもやはりスポーティな走りは外せない気持ちが強いのだな……ということがヒシヒシと伝わって感じられた。
(写真:島崎七生人)
※記事の内容は2025年3月時点の情報で制作しています。